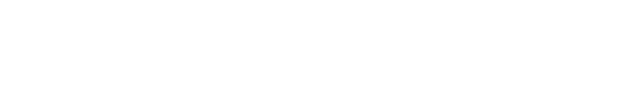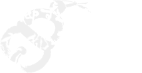「すぐき」について
「すぐき漬」といえば、千枚漬、しば漬と並び、京都の冬の代表的なお漬物です。これらは「京都三大漬物」と呼ばれ、おいしい冬の味覚として京都をはじめ、全国の方々に愛されてきました。
「すぐき漬」は「すぐき」と「塩」だけで漬け込んで作られ、乳酸菌による発酵作用による味わい深い酸味が特徴です。
「すぐき」がどこでどんな風に栽培され始めたのか、また、
おいしい「すぐき漬」とはどのような漬物なのか、ご紹介させていただきます。
すぐきとは

「すぐき」は【酸茎】とも書き、別の名ではスグキナ(すぐき菜)、スイクキ(水茎)、カモナ(賀茂菜)とも呼ばれています。なお、京都では「すぐき」といえば野菜としてのすぐきだけではなく、「すぐき漬」のことも意味します。
「すぐき」は、アブラナ科の二年草でカブの一系統。根の部分は短い円錐形で、長さは20㎝程度。大根を短くしたような形をしています。
葉は肉厚で濃緑色をしており、根の大きさの割には大きな葉をしています。花は「アブラナ科」だけに、菜の花とよく似た花を咲かせます。
起源と歴史について

「すぐき」の歴史は現在から400年ほど昔の桃山時代にまで遡ります。 上賀茂神社の社家(しゃけ:神社に仕える氏族やその家)が賀茂の河原で見つけたカブに似た珍しい植物を持ち帰って植えたのが始まりだという説や、御所から賜った植物を植えたのが始まりだという説。諸説ありますが、いずれにしても上賀茂神社の社家の間で栽培が始まったとされています。 最初は社家の屋敷内のみで作られていましたが、江戸時代末期頃からは一般の農家でも作られるようになりました。ただし、その頃はまだ一般の畑でも自家用や贈答用としてわずかに栽培する程度だったようです。一般に普及しはじめるのは明治維新以降です。
「高級贈答品」
「すぐき漬」は江戸時代初期の頃から上賀茂の特産漬物として、毎年初夏の頃になると賀茂社家の手によって洛中(京中)に贈られるようになりました。御所をはじめ公家の諸家や文人墨客(詩文・書画などをたしなむ人)など、上層階級の人々から「夏日の珍味」として賞味されていたと言い伝えられています。(この頃、すぐき漬は夏前に漬け上がる漬物でした。) 江戸中期以後は、「すぐき漬」の贈答が上賀茂社家の間で年中行事として慣例化し、社家に残る古文書にそのことを示す文章が書かれています。「すぐき」は、料理の食材として使用することが難しく、漬物になるべくして生まれた野菜であるといえます。
上賀茂固有の種と技術
文化元年、当時の所司代から出された『就御書口上書』で、「すぐき」を他村へ持ち出すことが禁じられました。「すぐきはたとえ一本といえども他村へ持ち出すことを禁ず」と朱書きされており、栽培技術はもとより、種一粒たりとも持ち出されることがありませんでした。それゆえ、この上賀茂の地にのみ、「すぐき」の貴重な発酵技術が今に伝わることとなったのです。
すぐき漬の製法
京都・上賀茂の名産すぐき漬は「すぐき」と「塩」だけで漬け込み、
天然の植物性乳酸菌の作用によって漬け上げる漬物です。
なり田の「すぐき漬」は「塩」以外の調味料及び添加物は一切使っていない無添加の漬物です。
味は、乳酸菌の発酵作用による、とても深みのある酸味が特徴です。
上質な天然塩だけを使い乳酸発酵をさせる上賀茂固有の漬け込み技術、そして長い歴史と、伝承の心が「すぐき漬」の味を磨きあげてきました。この「すぐき漬」がどうやって作られるのかをご紹介いたします。
栽培と収穫

「すぐき」の種まきは8月末から9月初旬に行われ、何度か間引きをし、11月から12月にかけて収穫を行います。 「間引き」は3回行います。間引き菜は壬生菜に似ていますが、独特の香りと風味があり、浅漬にして、季節限定の販売を行うことがあります。 最終収穫のことを「本立て」といい、午後まで待って行います。(朝は夜露に当たったすぐき菜の葉が折れてしまうため)陽に当たってしんなりする時分に、収穫を始めます。 種まきから収穫まで約80日かかり、収穫される「すぐき」は種まきした量と比べれば、20%以下と、実に限られた量です。
荒漬け

収穫した「すぐき」は、表面の皮をむいた後に「いため桶」と呼ばれる大きな樽に塩をたっぷりかけ、一昼夜漬けます。これが「荒漬け」です。
本漬け

荒漬けした翌日、「すぐき」を一本一本丁寧に水洗いして本漬けに取りかかります。通称「反樽」と呼ばれる樽にぎっしりと渦巻き状にすぐきを並べていきます。一段ごとに塩をふり、4段ほど重ね、最後に空気に触れないように葉で覆ってフタをし、重石をかけます。
「天秤押し」

重石のかけ方は「すぐき漬」独特の「天秤押し」というやり方で、長さ4~5mほどの丸太棒の一方を固定させ、もう一方の先に重さ10Kgほどの重石を3つほど下げて樽のフタを押さえる方法です。いわゆる「テコの原理」を利用したもので、フタには重石の10倍程度の圧力(約300Kg)がかかります。
「室」での熟成

重石をかけて日数が経つと水が出て「すぐき」のかさが減ります。その都度水を捨て「追い漬け」を行い、塩漬が完了した後「室」の中へ入れます。「室」とは、木炭や電気を熱源とした加熱室で、人工的に発酵を促す為の部屋です。(昔はこの「室」がなかったので、漬け上がるのに5月ごろまでかかりました。)「室」は、40度程度に暖められており、1週間ほどこの中に入れておくと、独特の酸味を持った京都名産「すぐき漬」ができあがります。
種の収集と管理

収穫前に葉に勢いがある良質の「すぐき」を選定し、その株は収穫せずに残しておきます。やがて春になると、残された株は花を咲かせて実をつけます。種は黒茶色のケシ粒大の小さなもので、その種を収集・保存しておきます。いい種を残すために農家同士で種を交換することもあります。次の年の「すぐき」は、この種を使って栽培します。 上賀茂の東隣りの松ヶ崎は、かつて菜の花(菜の花漬に使用)の産地でした。しかし、「すぐき」と交配してしまうのを避けるため、上賀茂一帯では菜の花は作ってはいけないことになっています。上賀茂の農家は、こうして自分たちの「すぐき」を代々守ってきたのです。
すぐきの食べ方
なり田がおすすめしている、すぐきの美味しい食べ方をご紹介します。
葉の部分は塩のかたまりが残っていたら、軽く水で洗ってください。

カブの部分は上図のように5ミリ程度の厚さに切ってください。

葉の部分はみじん切りにして、カブの部分と一緒にお皿に盛りつけてください。
お好みに合わせてお醤油を適量かけてお召し上がりください。
七味唐辛子と炒りごま、もしくは山椒を少量おかけいただきますと格別の風味を増します。

時候慣れすぐき
上賀茂で行われるすぐきの漬け込み作業は、上賀茂の冬の風物詩とも言われ、すぐきは冬が旬だと認識されています。
11月中旬〜下旬に収穫されたすぐきが漬け上がるのは12月上旬。
温度管理された室での発酵は約一週間と、漬け込み期間は短くさっぱりとした酸味と
すぐき自体が持つ味をお楽しみいただけるが冬の新漬すぐきです。
樽出しせず、そのまま発酵させた「時候慣れすぐき」は、発酵が進み深い酸味が特徴。
夏まで発酵を続けたすぐきが食べられるのはなり田だけなのです。

なり田だけの時候慣れ生すぐき
冬に漬け上がるすぐき漬ですが、なり田では全て樽出しするわけではありません。樽出しが行われなかったすぐきは、気温の上昇とともに自然と発酵が進んでいきます。樽の中で熟成したすぐきは「時候慣れすぐき」と呼ばれています。冬の新漬とはまた違ったしっかりとした酸味を感じられ、乳酸菌も豊富。 なり田では、夏でもこの樽出しの生すぐきの販売を行なっています。 一般的に夏に売られているすぐきは、発酵が進まないように熱処理が行われたもの。この真空パッケージ化・熱処理のおかげで保存期間を長くすることが可能になります。 そのとき、すぐきに含まれる乳酸菌の発酵の力は弱まりますが、弱まった菌でも私たちのからだにとって、プラスに働く力は備わっています。
発酵し続ける夏すぐき
なり田が販売する「時候慣れ生すぐき」は、熱処理を行なっていないためそのまま置いておくと、日々発酵が進んでいきます。
そのため賞味期限は短いですが、生きたままの乳酸菌がいます。
長期間、樽の中ですぐきを熟成させることは難しく、品質管理に手間と時間もかかります。
なり田では、日々すぐきの状態を確認し、職人の手によって徹底的な管理を行なっています。
これは、300年以上すぐき漬を作り続けてきたからこそ、できること。
自信と誇りを持って、皆様へすぐきをお届けしています。